 |
5時20分頃 鉾立登山口に到着。
ブルーラインの途中からすでに霧が出ていたが、やっぱり昨日と同じ風景。
あ、まあ、昨日よりはやや霧が薄いかな。
しかし、駐車スペースには20台以上の自動車が駐車していた。
みんな登る気満々だ。
が、この濃霧で登山中止を決めた人もいるらしく、駐車場を出る自動車もあった。 |
 |
 |
5時26分 支度をして登山開始。
霧が濃いので、最初から雨具を装着した。
お地蔵さんが見守る登山口である。
このお地蔵さんは登山者を守っているワケではなく、ゴミはもって帰れと言っている。 |
 |
 |
5時28分 東雲荘 TDKの山荘
道はこの東雲荘までは軽トラくらいなら入って来れる道である。
その先はコンクリートのなだらかな階段になる。 |
 |
 |
5時35分 鉾立展望台
真っ白なので、展望がきかないのは分かっている。
ので、立ち寄らない。 |
 |
 |
左側が切れ込んだ、手すりのある道になる。
霧がなければ、展望がいいかもね。 |
 |
 |
木道も出てくる。
この最初のなだらかなあたりで、意外に花が多く、ヨツバヒヨドリ、オミナエシ、ヤマハハコ、エゾシオガマなどが見られた。 |
 |
 |
木道が終わるといよいよ登りになる。
石の階段だ。 |
 |
 |
ダンナはあまりにも蒸し暑いので雨具を脱いだ。
まだ霧はみっしりと濃いんだけど。
石の階段は続く。 |
 |
 |
平坦になったり、 |
 |
 |
階段になったり、それにしてもずっと石が敷き詰められた道である。
コバギボウシ、ノリウツギ、ウゴアザミなど道の脇に咲いている。 |
 |
 |
6時05分 秋田山形県境
そういう道標だったことを、あとで写真を見て初めて知った。
ここまでが山形、この先は秋田県である。 |
 |
 |
石畳の道が続く。
ここの石畳は歩きやすい。 |
 |
 |
それにしても霧が晴れない。 |
 |
 |
足元にこんもりとコバギボウシが群れて咲いている。
どうもお花畑のようだ。
おや、シロバナトウチソウやイワイチョウの姿が見えはじめたぞ。
ここは、湿原か? |
 |
 |
石畳がなだらかに登り始める。
イワショウブもあるじゃないの。 |
 |
 |
霧の中、たぶんお花畑の石畳を登る。
ウメバチソウも咲いているぞ。 |
 |
 |
ぐんぐん登る。
キンコウカだって咲いている。 |
 |
 |
6時45分 賽の河原
えー、賽の河原って道標が出てきたぞ。
どう見てもお花畑じゃないの。
ってか、霧で近くしか見えないけどさ。
なんだか霧が粒になって雨っぽくなってきた。
ダンナも雨具を着なおした。 |
 |
 |
どこでもケルン。 |
 |
 |
ケルンを通り越すとけっこうキツい登りになる。
両側が笹で、見通しがきかない。
と、思うと左側が大きく削れた沢のような場所を登って行く。 |
 |
 |
7時26分 御浜
ハクサンシャジンの花が見えはじめたな、と思ったら、御浜に着いた。
第一の目標地点である。
とりあえずホッとする。 |
 |
 |
道はどっちだ?
御浜小屋へ鳥居をくぐって登って行く。 |
 |
 |
小屋の裏手にあたる方向に道がある。
裏手は、どうやら岩ゴロゴロの場所らしいのだが、真っ白で分からない。
数人の人が休憩中だったが、我々は休憩しないで先に進む。 |
 |
 |
小屋の裏手には一応、方位盤がありましたよ。
東西南北しか書いていなかったけど。
右は、チングルマの花穂。 |
 |
 |
小屋の裏手に細い道がついていて、そっちに歩いて行く。 |
 |
 |
と、いきなりガレガレの斜面が現れて、どう進んでいいのやら分からなくなる。 |
 |
 |
しかし、この斜面がお花の宝庫。
ハクサンイチゲ、マルバタケブキみたいに見えたトウゲブキ、トウヒレンかと思いきやオクキタアザミなど、東北の花も見られる。 |
 |
 |
7時46分 小さな祠
岩なんだか祠なんだかよく分からなかった。
ハクサンシャジンがまあ、こんもりと咲いている。 |
 |
 |
とにかく岩を登る。
我々は遅いので、次々と後続の人たちに譲って行く。
あ、ハクサンフウロ。 |
 |
 |
真っ白なので、どんな状況かわからないが、岩々と花々の競演する場所だ。 |
 |
 |
ビンクのハクサンシャジンやらハクサンイチゲの咲初めって紫っぽいのね、と思ったり。 |
 |
 |
7時58分 御田ケ原
きっと広いお花畑なんだな、見えていれば。 |
 |
 |
ここにもケルンできているし。 |
 |
 |
ところで、この御田ケ原から下る道はものすごく整備された石畳の道だった。
まるで公園のようで、自動車も走れるんじゃないかというくらいだ。
そして、その石畳の両脇に今回見たくて仕方なかった、チョウカイアザミが咲いていた。
思った以上にたくさん咲いていてびっくり。
花の裏側のガクにあたる部分が青っぽくて、なんだか神秘的な色だ。 |
 |
 |
8時13分 御田ケ原分岐
あとで調べたら鳥海湖の向こう側を通って万助道、二の滝道に至るコースへの分岐らしい。
が、なにせ真っ白。
我々はここまでで鳥海湖の姿も見ていないのだよ、はい。
ここがいわゆる鞍部になる。長い下りはここまでで、ここから登りだ。 |
 |
 |
ずっと石が敷かれた登りが続く。
エゾシオガマやヤマハハコなどが咲いている。 |
 |
 |
8時23分 八丁坂
オクキタアザミはごっそりと咲いていた。 |
 |
 |
八丁坂の少し先でさすがの石畳も終わり、いきなり岩が崩れたような場所になった。
何か、上のほうで崩落でもあったのか、という感じの岩だらけの斜面である。
でも、反対側はお花畑なのよ。
トウゲブキ、ハクサンシャジン、ニッコウキスゲなどなど、色とりどりだ。 |
 |
 |
む、どうやって この斜面を登るのだ、と困っていると、ちゃんと白いペンキの矢印がついていた。
このあたりからウサギギクも見られ始めた。 |
 |
 |
ペンキにそって歩けば大丈夫。
でも、雨っぽいので要注意。
わー、キスゲも団体で咲いている。 |
 |
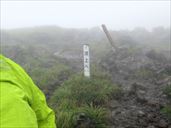 |
8時39分 頂上へ①
むむ、なんだ、この道標は?
①って、何番まであるんだ、これ。
8時41分 七五三掛
ベンチがあり、休んでいる人がいた。
さて、この七五三掛で分岐しているはずなんだがな。
アプリを開いて見ていると、休んでいる人が分岐はもう少し上みたいですよ、と教えてくれた。
なかなか分かりづらい。
ちなみに、七五三掛は、「しめかけ」って読むんだそうだ。 |
 |
 |
七五三掛の先は木道になっていた。
これがまた急な登りの木道で、雨で濡れているので、滑って怖い。
でも、すぐに終わって階段状の道に。 |
 |
 |
両側を木で固められた、まるで排水溝のような道になったぞ。
たぶん崩れ止めだとは思うけど。
その先は泥に岩が埋まったような登りになった。 |
 |
 |
8時51分 外輪山方面分岐(の手前)
ちょっと登るだけかと思いきや、だいぶ登ってやっと標識が登場した。
ベンチもあって、分岐らしい。
だが、しかし、ここは分岐ではない。
紛らわしいじゃないの。
我々が行きたい千蛇谷方向にはロープが張られていて、行くことができない。
つまり、もうちょっと登れ、ということだ。 |
 |
 |
これがまあ、けっこうな岩場をガッツリ登る。
8時56分 外輪山・千蛇谷分岐(こっちが本物)
古い道標と、ちゃんと正面に小さいがここは外輪山、千蛇谷分岐と書かれたものがある。 |
 |
 |
いやしかし、その千蛇谷に向かう道、左写真みたいに岩にへばりついて行かないと道に出られない感じなんですよ。
危険はないんだけど、分かりづらい。
でも、そのへばりついて出た先にダイモンジソウ発見。 |
 |
 |
また排水溝みたいな道になった。
霧の向こうにホソバイワベンケイ。 |
 |
 |
なんか、下るなぁ。
う回路かなんかなのかなぁ。
この時点で我々はかなり下らないと谷にたどり着かないという認識はない。
下るなぁ。
下るなぁ。
いつまでも下るなぁ。
道、間違っちゃったんじゃないの?
アプリで確かめると間違ってはいない。
帰りにはこのとんでもない下りを登るのか?
今からげっそりする。 |
 |
 |
結局15分弱下った。
先方にうっすらと白い雪の姿が見えてちょっとたじろぐ。
今は8月。まだ残っているんだ。
9時09分 千蛇谷
案内標識が傾いているぞ。 |
 |
 |
9時11分 頂上へ②
ここで②ですか。
①からだいぶ離れている気がする。 |
 |
 |
岩を慎重に下って雪にとりつく。
ロープで通る場所を示してくれているので安心だ。 |
 |
 |
上流のほうを見てみる。
けっこう大きな雪渓のようだ。 |
 |
 |
雪の谷底から先は当然登りになる。 |
 |
 |
岩っぽい登りをひいひい登って行く。 |
 |
 |
9時23分 頂上へ③
岩を登り切ったら草原に岩がゴロゴロ頭を出しているような風景が広がっているらしい場所に出た。
らしい、というのは、相変わらず霧なので、全貌が分からなのだ。
でも、草原なのでたくさんの花が咲いている。
スダヤクシュなんかも現役だ。
高原蝶のベニヒカゲも雨にも負けずに飛んでいる。 |
 |
 |
アザミの仲間もごっそり咲いている。 |
 |
 |
草原の中に岩がゴロゴロといった感じの場所。
矢印がありがたい。 |
 |
 |
登りが急になったあたりで、視界も開け、草原と岩の風景になったらしい。
そして、辺り一面、アオノツガザクラだらけになった。
いな、本当に一面アオノツガザクラ。
こんなにたくさんのアオノツガザクラを見たことがない。 |
 |
 |
9時45分 読めない道標と、その上に「ふくらヨリ八里」の石碑
ふくら、という集落に石工さんがいて、その人たちが石畳の石を作ったり運んだりしたらしい。
時々石に名前が彫られたりしている。 |
 |
 |
9時48分 頂上へ⑤
あれ、④はどこに行った。見落としか?
途中、追い抜いて行った若者たちが、この番号は10までなんですかね、と言いながら歩いていた。
うむ、謎だ。 |
 |
 |
それにしても登る。
とにかく登る。
9時56分 頂上へ⑥
ヒオドシチョウがいたぞ。 |
 |
 |
10時13分 頂上へ⑦
登る。 |
 |
 |
10時33分 頂上へ⑧
何が何でも、とにかく登る。 |
 |
 |
10時47分 頂上へ⑨
ぜいぜい言いながら、立ち止まりながら、水分補給しながら、じりじりと登って行く。 |
 |
 |
草原の中の岩の斜面は続く。
おや、あの紫はハクサンシャジンじゃないぞ、イワギキョウだぞ。 |
 |
 |
草の姿が少なくなり岩が多めになってきたな。
時々階段状に岩がつなげられている。 |
 |
 |
お、イワブクロ。
花についた毛に霧がまとわりついている。 |
 |
 |
11時04分 御室(頂上小屋)
霧の向こうに小屋が見えてきた。
おお、やっと頂上小屋か。
ここからまだ新山に登らなくちゃならないけど、もう息も絶え絶えだぞ。 |
 |
 |
と、いうことで、腹を満たすことにした。
昼食休憩。
おにぎりをホテルに忘れてしまったことが悔やまれるが、菓子パンを多めにもって来ていたので大丈夫。
お昼を食べていると、霧が一瞬だけ晴れて、新山の姿がうっすらと見えた。
えっ、あれに登るの?
と思わず言ってしまったら、もう登り終えた登山者が
「岩だけど、滑らないから大丈夫。ちゃんと三点確保すれば心配ないよ」と言ってくれた。
いや、怖いんじゃなくて、岩ばっかりで高いじゃないの。
手持ちのデーターでは小屋から20分で新山山頂というけど、それ、嘘だろう~と心の中で嘆く。
右写真の小屋の奥にうっすらと見えるのが新山。
霧で本当に一瞬しか見えなかった。 |
 |
 |
昼食後にトイレを借りて、ここが大物忌神社か、と確認して、いざ新山にチャレンジだ。 |
 |
 番外
番外 番外
番外