

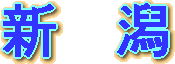 48−8
48−8新潟の滝48(2003年9月の訪問時のレポ)へ
新潟の滝48−2(2005年9月の訪問時のレポ)へ
新潟の滝48−3(2006年9月の訪問時のレポ)へ
新潟の滝48−4(2007年8月の訪問時のレポ)へ
新潟の滝48−5(2008年8月の訪問時のレポ)へ
新潟の滝48-6sp(2009年8月の滝オフのレポ)へ
新潟の滝48-7(2010年8月と9月の訪問時のレポ)へ
新潟の滝48−9(2013年7月と9月の訪問時のレポ)へ
 本城の滝 (2012年夏-1) 8月15日の本城の滝。 一番下の段が雪で覆われている。 ぽっこり開いた穴が面白い。 今年も大雪ではあったが、 猛暑が続いたために 雪解けは進んだらしい。  本城の滝 (2012年夏-2) 8月19日の本城の滝。 最下段の上の雪がごっそり減っている。 そういえばずっと暑かった。 きっと8月中には全体が出現することだろう。 |
2012/8/15(水)、8/19(日) 本城の滝 魚沼市 (落差40メートル?) 毎年訪問している本城の滝だが、昨年2011年は訪問することができなかった。 と、いうのも、2011年7月にこの地方を局地的な豪雨が襲い、国道352号線が長い間通行止めだったのである。 災害から1年後の2012年でも、本城の滝のある銀山平キャンプ場入り口からほんのちょっと先(福島方向)に行った遊覧船乗り場から国道は通行止め。この先の福島県へは行けない状況だ。  閉鎖されている国道352号線。 閉鎖されている国道352号線。そんな状況で、本城の滝自体ちょっと心配だったが、キャンプ場での入り口では別段行けないとも言われないままゲートを開けてもらえた。 最初に行ったのは夏休み本番の時だったので、途中の林道では子供などがいたりして、滝にも人がたくさんいるだろうか、と思われた。 途中の林道は水害の爪痕などはほとんどなく、例年どおり通行できた。 駐車スペースには2台ほどの自動車。我々のあとからももう一台。 メジロアブの攻撃を受けるので慌てて仕度をして出発した。 とにかく暑い日で、ちょっと歩くだけでも汗が流れる。 しばらく歩くと、あら、蝶の姿が。  オオゴマシジミは只今産卵中。 オオゴマシジミは只今産卵中。希少種の蝶で、これを狙いに来ているコレクターも大きな網を構えていたりした。 毎年楽しみにしている花は、まだ8月ということもあってやっと開いたばかりだ。   ツルニンジンとジャコウソウ。 ツルニンジンとジャコウソウ。 ヨツバヒヨドリにヒメキマダラセセリ。 ヨツバヒヨドリにヒメキマダラセセリ。さて、滝。 今年は雪が多かったので、もしかしたら8月ちゅうではまだ姿も見せてくれていないかも、と思っていたが、最後の急な坂を登ると水音が聞こえた。 雪が一番下の段の上に覆いかぶさって、芸術的な穴を見せている。が、上の段は綺麗に出ていた。 一昨年の8月にはこのあたりにコバイケイソウが咲いていて驚いたのだが、今年はどうもコバイケイソウの花には当たらなかったようだ。 では、期待しているハクサンコザクラはどうだろう。 坂を下って行くと、あら、滝前に男性がいる。 ダンナが滝前の斜面を指さすので、そちらを見ると、うわわわ、思った以上の数のハクサンコザクラが咲いていた。 ただ、かなり急な斜面なので近づくことができない。 滝前の男性が我々が斜面を見ているので心配して、向こう側に鎖があって降りられるのだ、と教えてくれた。 わかってまーすと答えて、我々も滝前に行く。 男性は腕章をつけた観察員で、本城の滝に通い詰めているらしかった。少しだけハクサンコザクラやヒメウメバチソウの情報を話して分かれる。 それにしても、ハクサンコザクラ。よい条件だとたくさん咲くのだと分かった。   滝左岸斜面のハクサンコザクラ。 滝左岸斜面のハクサンコザクラ。ハクサンコザクラを撮影してから、少し下流の河原に行って昼食。スノーブリッジが残り、寒いくらいの天然クーラーだった。  もやがかかっているスノーブリッジの下。 もやがかかっているスノーブリッジの下。その4日後、いつも会えるキベリタテハに会えなかったので、ダンナだけもう一度本城沢を訪れた。 たった中3日なのに雪がかなり消えていて、花も色々と開いていたそうな。 滝の右岸の岩の上にもハクサンコザクラの群落があり、これまた毎年ここに来ているご夫婦に教えてもらったとか。 おそらくどこよりも遅くハクサンコザクラが見ることができる最も標高の低い場所なんじゃなかろうか、この本城の滝の周辺は。 この特殊な植物群に魅せられて毎年訪れる人たちがたくさんいるということが分かった。 もちろん、キベリタテハにも遊んでもらったそうですよ。   ツルニンジンもだいぶ開いた。 ツルニンジンもだいぶ開いた。  右岸のハクサンコザクラとキベリタテハ。 右岸のハクサンコザクラとキベリタテハ。 |
|
| 交通 本城の滝への行き方については、新潟の滝レポート48を参考にしてください。 |
||
新潟の滝もくじ ときどき週末温泉族になる んがお工房の日本百名滝めぐり 掲示板